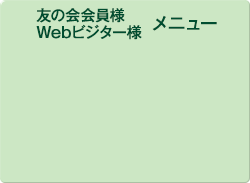「ハラスメント耐性」を検索したらAIによる概要が
出て来ました。
読んでみると、確かにと思えたんですね。
「ハラスメント耐性」は、文字通りにはハラスメント
(いじめや嫌がらせ)に対する耐性を指しますが、
その捉え方や評価には注意が必要です。
短期的な業務効率の向上や規律ある人材確保を目的
として「ハラスメント耐性」を優先することは、
職場の硬直化や創造性不足、離職、メンタルヘルス
問題の増加を招き、企業の競争力低下に繋がる可能性
があります。
現代ではワークライフバランスを重視する価値観が
高まっており、このような考え方は逆効果になり
かねません。
ハラスメントの防止には、「ハラスメントをしない、
させない、許さない」という職場環境の構築が大切
です。
読んで最初に思ったのは、「このシリーズ、わざわざ
書く必要なかったなあ」ということですね。
AIは恐らく、例えば「ハラスメント耐性」について、
自分で考えて判断を下すというよりも、多くの意見を
集め、多数派と考える意見を紹介しているだけ。
であれば、「ハラスメント耐性」というものが仮に
あったとしても、その性質を否定的に考える人が多い
ということになります。
「むしろ企業が求めているのは、指示待ちではなく
自ら考えて行動し、改善につなげられる主体性です。
そうした“進化した体育会系”は歓迎されつつありますね」
ただ、記事の中では上記のような指摘もあり、記事の
否定するつもりはないです。
でも、「指示待ちではなく自ら考えて行動」。
これなどは、別に運動部出身のかただけの特性では
ないですし、運動部出身でも該当しない人もごまんと。
従って、運動部だからこそということにはならないです。
2025.9.13
でも、運動部。私は楽しかったです。
余分なものは理不尽なしごきと上の立場を利用した
強要だけでした。
あと、記事の中にあった内容で共感できなかった
ことは、「OB・OGによる外部とのつながりによる
有利さ」ですね。
これって、言ってみれば縁故を利用して正当な競争を
かいくぐってという意味になります。
腹を割って話せるということはあるかもしれませんが、
同じ運動部、同じ学校出身ということで便宜を図る
ようなことがあれば、それはそれで既にNGです。
そんなことを利点として挙げる説明の記事、全然共感
は出来ません。

ハラスメント耐性があるって?⑥